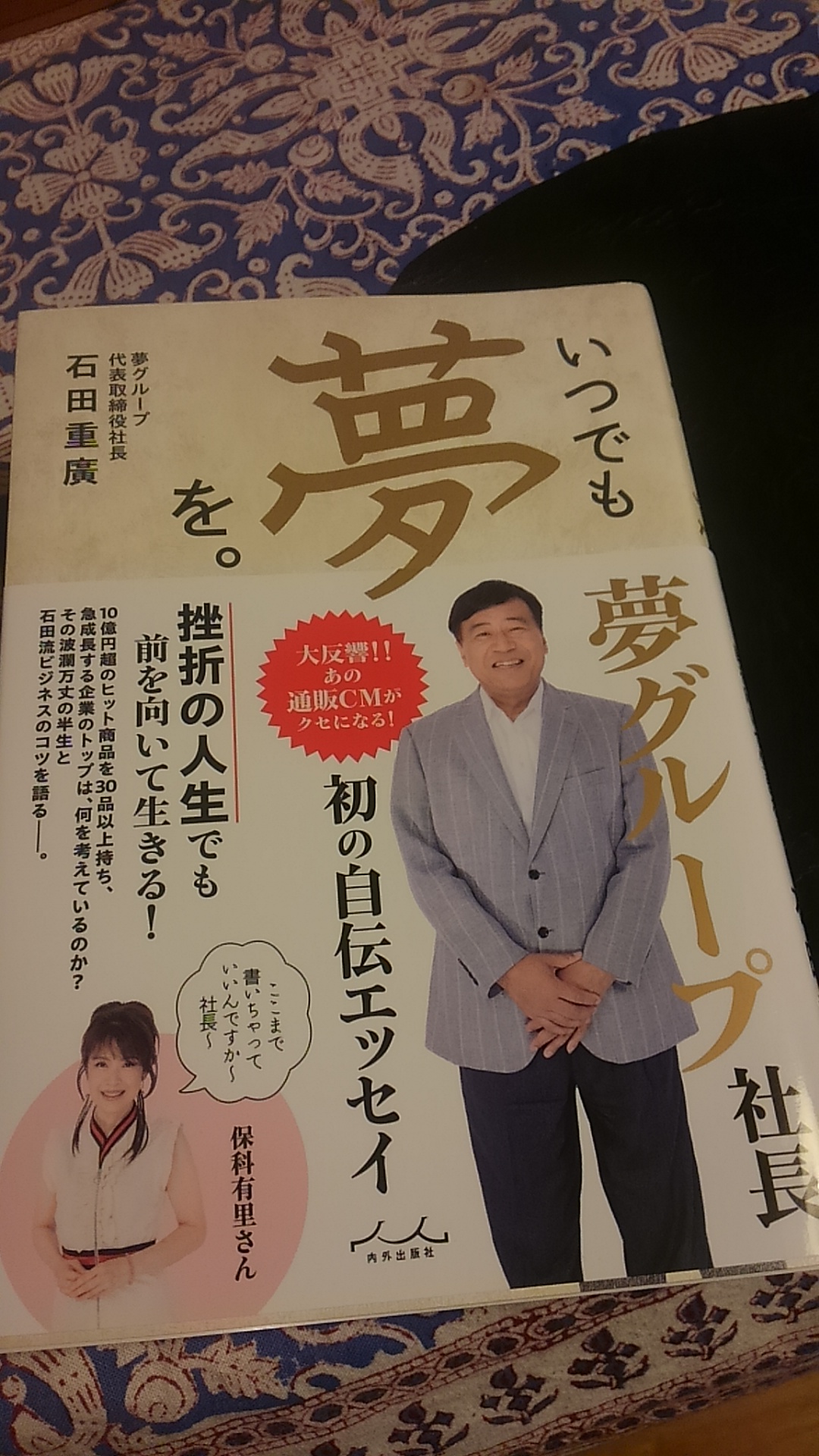得意だった体育も、一度だけCになってしまったことがあります。
小学校6年の1学期に、オールCを取ったときのことは今でも忘れません。
「これは困った、親にも何をやってるんだと叱られるだろう」
と思って、
先生に「どうして体育がCなんですか?」と聞きました。
すると先生は、
「石田、お前覚えているか? 授業中にサッカーの試合をやったときに、
自分たちのゴールにボールを蹴り入れただろう」
と厳しい顔で話してくれました。
なぜかといえば、
同級生たちがあまりに下手で面白くなかったから、
味方のゴールにボールを蹴ってしまったのです。
「いいか、サッカーにはルールがあるんだ。ルールに従わないとダメなんだ」
ルールか……。
僕はのちに世のなかのルールというものに悩まされることになりますが、
これはルールを意識した初めての体験となりました。
(夢グループ代表取締役社長石田重廣『いつでも夢を』内外出版社、2022年、pp.40-41)
きのうにつづき「夢グループ」のことを。
手づくりのテレビコマーシャルの制作費が2~5万円というのも驚きですが、
この本を読むと、
社長の石田さんが、一見ルール無視とも思われるアイディアを
つぎつぎ形にしてきたかが分かります。
わたしも自分で会社を始めてから、
あまり意味を感じられないルールには、
なるべく縛られないようにしようと考えてきましたが、
石田さんは桁外れ。
中国から仕入れたシルクのパジャマのコマーシャルに社長みずから主演したとき、
ある女性の客から電話が入り、
「あの男性はシルクが似合わない」
と言われたのだとか。
また、
怒った客が電話してきて「社長に代われ!」と電話に出た者を怒鳴りつけ、
電話を代わって「ぼくが社長です」
と相手に告げたら、
「ウソをつくな! 社長は、自分のことをボクとは言わない!」
と、また怒られたのだとか。
石田さんがシルクのパジャマを着てもいいと思うし、
社長が自分のことを「ボク」と言ってもいいとは思いますが、
たしかに、
この辺りにも石田さんのルールに囚われない、
憎めない傾向は出ているようです。
・二ページを残して閑秋の暮 野衾