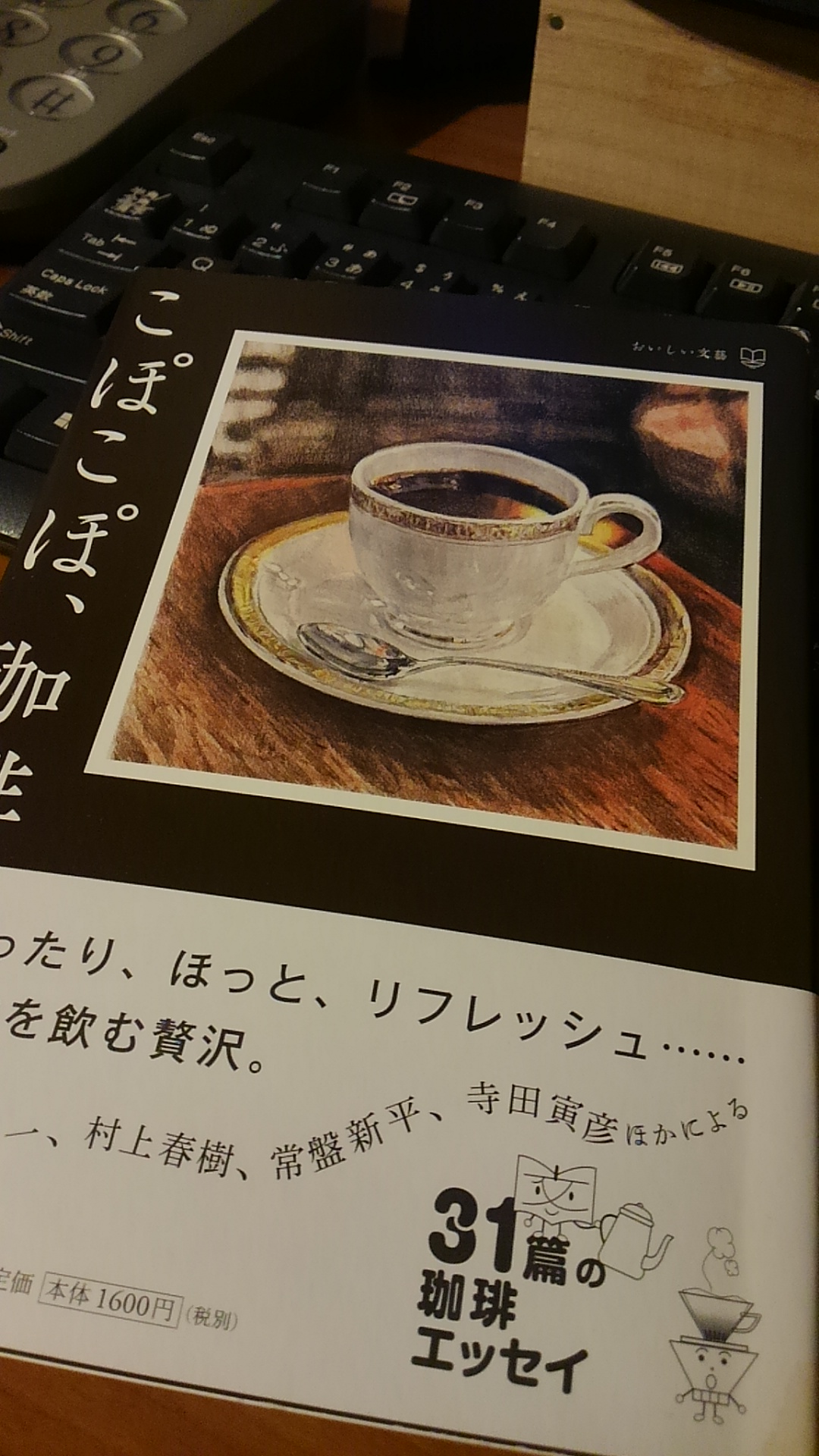このごろ思うところがありまして、
宮澤賢治のものをあれこれ読み返していたところ、
秋田生まれの
田口昭典(たぐち あきすけ)さん
という方の
『縄文の末裔・宮沢賢治』(無明舎、1993年)
という面白そうな本があることをネットで知りました。
さっそく古書で求め、読みました。
書名にあるとおり、
宮澤賢治が縄文の魂を持った詩人、童話作家である
ことを考察したものですが、
いろいろと共感し、
ふかく納得するところがありまして。
唐突ですが、
わたしのいまの問題意識は、
「耳の文化と目の文化」
であります。
縄文時代とそれ以前が「耳の文化」なら、
弥生時代以降は、
現代をふくめ、
基本的に、
「目の文化」ではないかと。
漢字が日本に伝えられたのは、
弥生時代の末期から古墳時代にかけてと言われており、
文字以外にも、
縄文と弥生では、
いくつか対比の視点があるようですが、
文字を知っている、文字を知らない、
という違い(その根底にある自然との付き合い方)
は、
これからの地球環境と、
そこにおけるいのちの営みを考えるうえで、
ほかのこと以上に大きなことのように感じます。
宮澤賢治の詩や童話に頻出するオノマトペと岩手の方言は、
賢治が耳の文化、
縄文の申し子であることの証であると思います。
いきなりですが、
星野道夫さんや畑正憲さんは、
二人とも多くの本を書いていますが、
根本は、
目よりも、耳のひと、
という気がします。
星野さんの愛読書の一つに、
アルセーニエフの『デルスウ・ウザーラ』があり、
生前、
星野さんがこれをボロボロになるぐらい読んでいたというのも、
なるほどと納得しました。
デルスウ・ウザーラは、
ナナイ族の猟師の名前。
それがそのまま作品のタイトルになっています。
弊社からこれまで四冊の本を上梓している小野寺功先生の「大地の哲学」、
梅原猛さんの構想、山折哲雄さんの賢治論、赤坂憲雄さんの「東北学」、
また、ガイア・シンフォニーの考え方と映像、
それらが深い処で交響し、しずかに鳴っているようです。
・口開けて鏡に白き歯の寒し 野衾