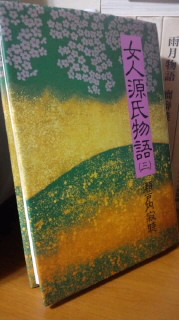・街灯の小さき音せり雪が降る
本を読まない子に親が最初に買い与えた本が、
夏目漱石の『こゝろ』と
森鷗外の『山椒大夫』でありましたが、
読もうとする意欲が湧かず、
そのときは
一ページも読んだか読まなかったか。
のちに気になり、
今度は自分の意思で
『こゝろ』を読んだら、
ひとのこころの気持ち悪さに初めて触れたようで、
本の世界に足を突っ込んだ形。
あれからずいぶん時間が経過しましたが、
『こゝろ』を思い浮かべるとき、
読み終えた文庫本の重さが手のひらに甦ります。
それから
忘れられないのは、
『ジャポニカ』と『広辞苑』
あの重さが好かった。
ぱらぱらページをめくるだけでよかった。
のちに平凡社の『百科事典』や
『大辞林』を使うようになりましたが、
始まりはなんといっても
『ジャポニカ』と『広辞苑』で、
あの喜びを何にたとえたらいいものか。
読む楽しさと持つ喜びを超えていたような気さえします。
中学校に入学し
自転車を買ってもらって、
雪解けの道を初めて走ったとき
風が目にしみてか、
うれしくてか、
分かりませんが、
涙が滲んだものでしたが、
それにちかいかもしれません。
重さと手触り感が始まり始まりでした。
紙の本は、
感動の始まりを演出できる
おもしろい媒体だと思います。
・雪積もりあの世へつづく道を踏む 野衾