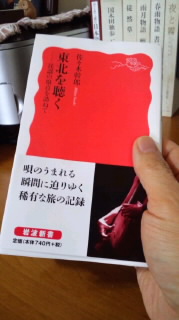・シャッターの羽や光りに溶けてゆき
佐々木幹郎さんの新著
『東北を聴く――民謡の原点を訪ねて』(岩波新書)
を面白く読みました。
本のオビに、
「唄のうまれる瞬間に迫りゆく稀有な旅の記録」
と書かれています。
また本のソデには、
「詩人が、津軽三味線の二代目高橋竹山とともに、
東日本大震災の直後に被災地の村々を行脚した稀有な旅の記録」
とあります。
稀有な旅。どんな?
わたしは秋田の生まれですが、
子どものころからよく民謡を聴いてき、
いまも、
とくに疲れて帰宅したときなど、
民謡のCDについ手が伸びてしまいます。
民謡が人間にとってなんなのか、
どういうはたらきをするものなのかを、
この本は、
疲れたこころに
深くやさしく寄り添うように語りかけてきます。
読む民謡と言っていいかもしれません。
十三ページから始まる「瓦礫の下の「八戸小唄」」には、
ひとりの主婦が地震の後、
仕事先から自宅へ戻ったときの
衝撃的な話が録されており、
絶句せざるを得ません。こんなことがあるのかと。
二〇一〇年一月、ハイチ共和国で大地震が起き、
死者は三十万人を超えた。
そのとき現地にいたハイチ出身の作家が、
自著に次のような言葉を記していることをこの本で初めて知りました。
「ホメロスにとっては、
もし神々がわれわれの上に不幸を降り注ぐなら、
それは人がそこから歌を生み出すためだ」
まさしく「瓦礫の下の「八戸小唄」」とかさなります。
この本を読むと、
民謡が生きてうたわれていることがよくわかる、
だけでなく、
民謡によってひとが生かされていることもわかる。
歌は、
それなくしては生きられない
“タベモノ”
といったたぐいかもしれない。
二代目高橋竹山さんの唄を聴いた老人が、
「寿命が延びた」と感想をもらした
のは唄を食べたからでしょう。
三月十一日、
この本を持って社員一同、
渋谷にあるサラヴァ東京に出向こうと思います。
三月の光りに浮れ土竜出ず 野衾